デザインのアイデアが欲しいという欲求にはさまざまな段階があります。
大きく分けると以下の6つです。
- A)ビジネスデザインとしての企画アイデアが欲しい場合
- B)プロダクト条件を決めるためにマーケティングアイデアが欲しい場合
- C)プロジェクトの骨子が決まりインパクトのあるビジュアルフックが欲しい場合
- D)デザイン条件を決めるために具体的なプロトタイプアイデアが欲しい場合
- E)デザインのテーマとなる全体観のアイデアが欲しい場合
- F)デザイン条件に沿ってデザインのディテールアイデアが欲しい場合
これらデザインのさまざまな段階でアイデアが必要となりネットや書籍・雑誌、展示会など情報を探すことになると思います。
ここではまずはA)、B)に対応する本を紹介します。
このニーズに対応するのが「何をデザインするかを考えるとき」に読みたい以下の五冊です。
宇宙船地球号操縦マニュアル
リチャード・バックミンスター・フラー著
• 1969年にOperating Manual for Spaceship Earthとして出版された翻訳本です。地球温暖化による異常気象など人類が直面している問題を50年以上前に示唆した本です。
• この本でバッキー(バックミンスターフラーの愛称)は、乗り換えが不可能な「地球号」を調子よく動かし続けるためには、地球を食い潰すことがないよう「より少ないものでより多くのことをなす」よう地球人は活動することが大事である旨を訴えています。
• この本をきっかけに、バッキーの本をさらに読み進めてもらうと「何を作ろうか」という議題に一定の答えが出ると思います。
• 地球人全員に読んで欲しいですが、特に文明の発達や文化の発展を仕事にしているビジネスパーソン、プランナー、エンジニア、デザイナーはこの本を読むことで、自身が作ろうとしているモノゴトが本当に必要なのか、存在意義を考えさせられる必読の書です。
イノベーションのジレンマ
クレイトン・クリステンセン著
• ハードディスクドライブを例題として、現状規格での改良と、新しい規格を採用し、サイズパフォーマンスを上げてきた歴史を、HD業界で覇権を握っていた大企業が合理的な判断を繰り返し未来の可能性を過小評価したために、小型化を優先した新興企業の新規格製品の後塵を拝することになった実体を解説しています。
• イノベーションに最も必要な要素は人が求め続けてきた本質的価値(ここでは小型軽量化でいつでも何処でも使えること)を追求することで、利益を上げ続けることを優先し、自己否定できない企業ではイノベーションは起きないことが良く分かります。
• 2007年の本でもう20年近く前の本で例となっている商材は古いですか、製品開発の最上流で企業経営に関わるデザインを考えるには、必ず知るべき内容です。
• 是非読むことをお勧めします。
WHY DESIGN NOW? なぜデザインが必要なのかー世界を変えるイノベーションの最前線
エレン・ラプトン/カーラ・マカーティ/マルチダ・マケイド/シンシア・スミス
• クーパーヒューイット国立デザイン博物館 現代デザインキュレーターの4人により、2010年ナショナルデザイントリエンナーレ「なぜ今デザインなのか?(Why Design Now?)」展をまとめた書です。
• エネルギー・移動性・コミュニティ・素材・豊かさ・健康・コミュニケーション・シンプリシティ・などの社会問題という問いに対し、この時点でのデザイン思考によって生み出されたアイデアを紹介しています。
• イントロダクションに書かれた「ーデザインプロセスは多くの場合、シンプルさの追求と重なる。多くのデザイナーは、目的を明確化した統一性のあるコンパクトなシステムを創ろうとしている。生産プロセスを簡素化して素材の種類と量を減らそうとするとき、シンプルさの追求から、デザインの経済的・倫理的価値と美意識が生まれてくるー」はデザイン思考が目指す指向性を上手く表現しています。
• 多くのカテゴリーの社会問題に対しての様々な取り組みが俯瞰でき、どのような視点から問いを立て、アイデアをだしたのかを沢山知ることができ、これから何を作るかということを日々考えているクリエイターに是非とも読んでもらいたい書です。
ことば・ロジック・デザイン|デザイナー・クリエイターを目指す方々へ
妻木 宣嗣 著
• 著者の大学での講義録をもとに再編集を行った本。
• 前半はデザイナーやクリエイターを目指す学生へ、言葉の重要性と思考方法を紹介しています。
• 後半は様々な事例を引き、クリエイターはもっとしっかりとクリエイションをして欲しいというメッセージが強く押し出されています。
• また現代の慣習は江戸時代から続いたコトが多く、常識は第二次世界大戦以降に生まれたものが多いため、そろそろ見直すことが大切だと訴えています。
• 例示されるカテゴリーが広範かつユニークで筆者の伝えたいという熱意を感じ、この本の面白いところであり特徴となっています。しかし例になっているモノゴトを既知な人にとっては理解できますが、未知の人にはもうすこし詳しく説明してもらったほうが、分かり易かったと思います。
• この本は題名の「ことば・ロジック・デザイン」からデザインをことばにするロジックについて書かれた本かと思いましたが、著者からクリエイターへ「どうデザインするかの前に、何をデザインすべきか良く考えて欲しい」というメッセージが詰まっている本で、著者の熱い思いが共感できました。
• クリエイターは是非読んでみて欲しいと思います。
デザイン脳を開く ー建築の発想法ー
宮宇地一彦 著
• 新しい事を考える創造を行う発想のメカニズムは3つあると説明しています。
• 一つはルールに従って演繹的に発想する方法。もう一つは様々な現存するモノから帰納的に発想する方法。そしてもう一つが仮説を設定して既成概念を壊して思考を飛躍させるという方法に分けられるとします。
• この本の面白いところは創造という発想もあるルールに基づいて起きるということを提案することで、後天的にも発想力は伸ばすことが可能ということを記しているところです。
• 創造の方法論を読むことで、直接的なアイデアが得られるわけではないが、この本を読んでいると様々な今までに情報を思い出し組み合わさることを誘発させてくれる本です。
• 「建築の発想法」という副題がついていますが建築に限らずデザインを行う人は、読んでみると不思議にアイデアが出てくる本です。機会を見て是非読んでみてください。
製品の存在価値を考えるには、企画の価値をどこに置くかの参考になります。振れ幅をひろく取り紹介していますので面白い視点を得られます。是非読んみてください。

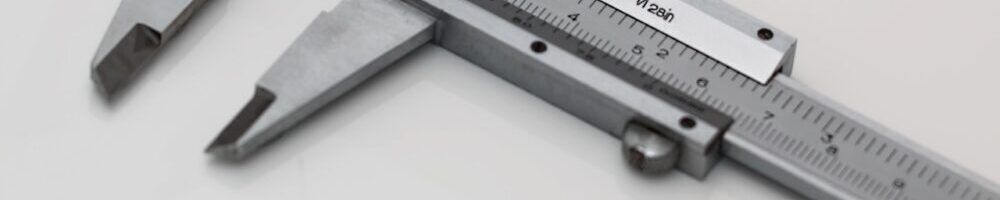
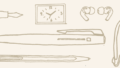

コメント